龍の神話ーメコンの「パヤナーク」
--- 伝説の「 龍 (リュウ) 」 は、実在する ? ---
| パヤ・ナークとは
「パヤ・ナーク」とは、インド伝来の「ナーガ神」で、日本風にいうと「蛇将軍」である。やがて、中国に伝わると「麒麟」、「鳳凰」、「亀」と並んで四霊神のひとつ、「龍」になる。「龍伝説」の始まりは、バビロニアというから、文明の始まりの頃から存在していたものらしい。実は、その伝説の「龍」が、実在していて、「メコン川」に住んでいるのである。 タイの「仏教」は、ヒンズー教、バラモン教とともに伝来したためか「蛇神(ナーガ)」との関係が極めて深く、寺院建築のあちこちに「パヤ・ナーク」のデザインが取り入れられている。 |
 |
1973年6月、ラオス基地に駐屯していた米兵たちが、捕えたというタイ語と英語で、書き添えられている。 額入りの写真が、「メコン川」沿いのみやげ物屋などで売られていて、タイの家庭の仏壇ちかくに「守り神」として飾られているのを見たことがある。 よく見ると頭部にはもっともらしい「修正」が施されている。(後述追記参照) |
| メコンのパヤナーク伝説 「伝説」というと、メコン川沿いに住んでいる人たちに叱られるかもしれない。 「チェンコン郡」のメコン川近くの村々には、たしかに自分の目で見たという人たちが大勢いる。 雨期のころなのであろうと思われるが、どんより曇った日などに、雨で増水したメコン川の水面に「パヤナーク」が、水面高く躍り出るのだそうだ。さながら、大昔打ち負かされた「ガルーダ神(空飛ぶ鳥の神様)」に、挑むが如く。こんなときは、メコンの漁師や船乗りたちは川に出るのをやめるそうだ。 「パヤナーク」の怒りに触れると、小舟は木の葉のようにひとたまりもなく転覆してしまうのだそうだ。 「パヤナーク様」は、「赤」嫌い(好み?)で、赤いシャツなど身に着けている人が乗っているとよく襲われるのか。赤いブラウスの女の子が、水底まで引きずり込まれて、浮かんでこなかったこともあったとのこと。このあたりの船乗りは、観光客でも、赤シャツの人は、嫌がるらしい。 10年以上前のことだが、「プート・メー・ナム・コン(メコン川の幽霊)」という連続ドラマが、ゴールデンタイムにテレビ放送されていたことがあるが、似たような話だったと記憶している。 また、外国にまで有名になってしまった話に「パヤ・ナークの火の玉」がある。旧暦11月の満月の夜、ちょうどその日は「オーク・パンサ」といって、坊さんたちの雨期安居明けの日に当たる。タイ東北地方「ノンカイ」の近くの「メコン川」の水面からたくさんの火の玉があがるらしい。 不思議な現象ということで、テレビ中継されたり、日本などからの取材もあるらしい。実際は、何か仕掛けがあるにちがいないし、みんな「迷信」と言ってしまえば、それまでのことだとは思うが、「迷信」が数ある社会というのは、何かしら心に豊かさを与えてくれるものだと思う。 |
 |
屋根の棟木の両端の「鯱(シャチホコ)」のように立っている飾り(「チョーファー」)も「パヤナーク」をデフォルメしたもので、いずれも、守り神としての意味がある。 余談になるが、破風側(ファサード)をごちゃごちゃと飾り立てないで、何もないのはシンプルでとても美しい。 チェンライに来られたら、「ワット・プラケオ」をたずねられることをお勧めしたい。「オーバーブルック病院」の西隣り。病院の旧本館、チェンライの街づくり当初に植えられたふるい並木、今でも現役のコロニアル風のゲストハウス。西側の小山の頂上には、チェンライのへそ、「ラック・ムアン」もある。このあたりはチェンライ旧開拓時代の中心地で、見どころがすべて集まっている。 |
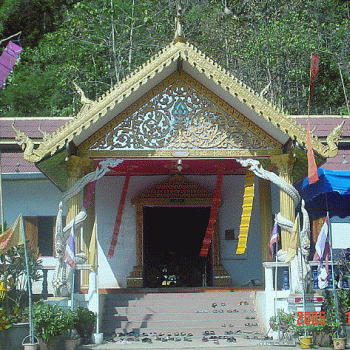 |
破風飾り、チョーファー、階段の手すり、みんな「パヤナーク」。 階段脇の柱に巻きついているのも、やはり「パヤナーク」。 お寺の「パヤナーク」はなぜかみんな「一角獣」である。角ではないのかもしれない・・・。 北タイの南部地方から中部タイにかけては、お寺の階段の手すりなどは、多頭の蛇(ナーガ神)で飾られている。ヒンズー教の影響が伝統的に守られているということかも知れない。 チェンライなど北タイ北部では、「メコン川」に実在する「パヤナーク」こそ「ナーガ神」そのものであると信じられていて、たいていのお寺で「蛇(ナーガ)神」の蛇ではなく「パヤナーク」になっている。 |
上の「パヤナーク」の写真は、「かたり」らしいことが判明。 「謎の巨大生物UMA」 や、「OOPARTS」 ( out of place artifacts ) によると、 「アカマンボウ目リュウグウノツカイ科リュウグウノツカイ」という深海魚の一種で、1996年、カリフォルニア州の San Diego, Coronado beach の浜に、打ち上げられたものらしい。 それにしても、“1973年、ラオス駐屯の米軍”などと、もっともらしい説明をつけたものだと、感心してしまう。民間信仰などの多くが、案外、こんなものなのかもしれない。 |